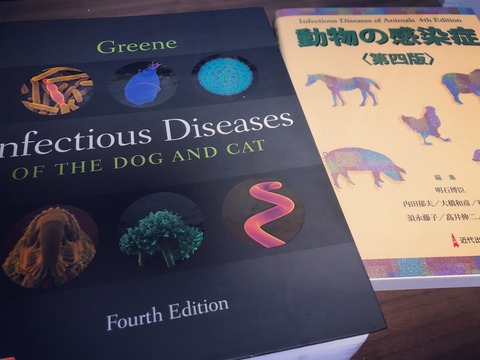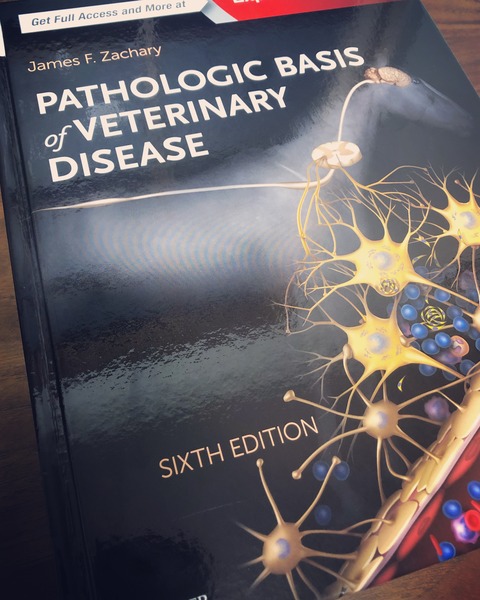結核は過去の病気と思われがちですが、日本では他の先進国と比較して発生率が高く、
毎年一万人以上が新たに感染している最大の感染症とされています。
https://www.jatahq.org/about_tb/
結核菌が属するマイコバクテリウム属菌は、細胞壁に豊富な脂質成分を含んでいて
酸に抵抗性を示すことから、抗酸菌とも呼ばれています
(酸だけでなくアルカリやアルコールをはじめとする消毒薬にも抵抗性があります)
抗酸菌はいくつかに分類されており、
①結核菌群(4種)、
②らい菌(ヒトのハンセン病の原因)、
③牛や羊など反芻獣のヨーネ病の原因菌、
そして、それらを除く抗酸菌をまとめて、
④非結核性抗酸菌(非定型抗酸菌)と呼ばれています。
非結核性抗酸菌は現在150種類ほどが知られています。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2414-related-articles/related-articles-454/7735-454r10.html
非結核性抗酸菌の多くは水系や土壌などの環境中や動物の体内に存在する常在菌で、
結核菌と比べて病原性が低いことから、日和見感染症の原因となることがあります。
結核とは違い、人から人への感染は起こりません。
人では高齢者の増加や免疫不全患者の増加、結核の減少などに伴って、
非結核性抗酸菌症の患者が近年増加しているそうです。
非結核性抗酸菌が人の皮膚に付着、あるいは体内に取り込まれても、
多くは通常の免疫系により排除されて感染が成立することはありません。
しかし、皮膚に傷があったり、衰弱していたり、免疫抑制剤を服用している、
などの条件が整うと感染することがあります。
非結核性抗酸菌が感染した場合、菌の増殖が緩やかで症状の経過が長く、
有効な薬剤も限られていることから、治療が難しい病気とされています。
また、環境中に広く常在していることから、非結核性抗酸菌が培養されても、
原因菌なのか、環境中の抗酸菌がたまたま培養されたのかの
区別が困難な場合があります。
さらに、培地上でも増殖が緩やかであること、雑菌が混ざっていると、
雑菌の増殖によって非結核性抗酸菌の増殖が分かりにくくなることがあるなどの
理由から、診断も難しいのが現状です。
非結核性抗酸菌症は人では近年増加していますが、結核と比較して診断基準や
治療法が確立されておらず、今後注意すべき感染症であると思います。
動物でも増えている非結核性抗酸菌症
人で問題になっている非結核性抗酸菌症は、動物にもあります。
淡水魚や海水魚、両生類には、昔から普通にみられました。
施設にもよりますが、水族館で死亡した魚を調べたらほとんどが
非結核性抗酸菌症だったということも経験しています。
爬虫類と鳥類でも時々みられ、
哺乳類では豚も非結核性抗酸菌症をみることがあります。
最近では、あくまでも私個人の印象ですが、上記の動物以外にも
色々な哺乳類に非結核性抗酸菌症が増えていると感じています。
元気がない、食欲がない、痩せてきたなどの異常を慢性的に抱えているにも
関わらず、原因が明らかではない動物を死後に病理解剖すると、
非結核性抗酸菌症だったということが時々あります。
分娩や長期間の移動、環境の変化など、ストレスで免疫が低下していたと
思われる動物が非結核性抗酸菌に感染した事例も経験しています。
最近では動物もがんが増えており、その他にも腎疾患や肝疾患を抱えながらも
薬や食事療法によって長期間体調を維持できるようになってきました。
そのせいか、がんの治療のために免疫抑制剤を長期間投与していた動物が
非結核性抗酸菌にかかった事例もあります。
非結核性抗酸菌症になると、複数の治療薬を長期間にわたって服用しなければならず、
治療にはかなり時間を要します。
動物でも今後、非結核性抗酸菌症が増えてくると思いますので、
診断や治療法の確立を期待したいです。
非結核性抗酸菌症の診断に関して困っていることがあります。
私は普段、様々な動物を病理解剖しており、
必要に応じて微生物検査を外部の検査機関にお願いしています。
しかし、非結核性抗酸菌症を疑って検査を出しているにも関わらず、
非結核性抗酸菌が培養されないことがほとんどです。
人と違って動物では、検査体制が整っていない部分がかなりたくさんあります。
動物専用の検査会社もいくつかありますが、
微生物検査に関してはなかなか信頼できる結果が返ってくることがありません。
微生物の種類だけでなく、血清型や遺伝子型、病原因子の保有状況など、
さらに踏み込んだ検査をしてくれるところがなく、いつも困っています。
結局、微生物の種類に応じて信頼できる研究者に個別にお願いしているのが現状です。
動物の死因究明センターを作って動物の疾病に関する情報を集め、
それを社会に還元したいという夢が私にはあります。
動物といっても非常に多様な種類があり、それぞれの動物ごとに様々な病気があります。
私たちは、そのうちのごく一部の病気のことについてしかまだ分かっていません。
動物の病気を知ることは、人の病気の理解にもつながると信じています。
また、近年世界的に問題となっている人の感染症の多くは、動物由来の感染症です。
動物の病気や死因を明らかにして、人や動物、自然環境に貢献したい。
そんな夢が実現できる日がいつになるか分かりませんが、そのときには、
信頼できる細菌、寄生虫、ウイルス、遺伝子、疫学などのエキスパートを
集めたいと思っています。(協力してくれる人、いないかなぁ)