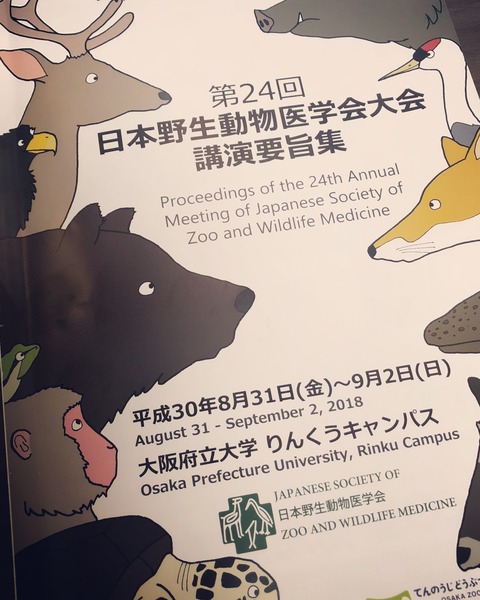前回の記事では、獣医における人工知能(AI)について取り上げました。
今回は、読み方は同じエーアイでも、オートプシー・イメージング(Ai)について考えます。
Aiは死亡時画像診断のことで、CTやMRIなどの画像診断装置を用いた死後の画像検査によって、
死亡時の病態や死因を検証するものです。
人では剖検率の低さを補うものとして、医療事故、異状死、外因死などの判断に
有用な情報を提供することで非常に注目されています。
私がAiの概念を初めて知ったのは大学院の学生時代、ブルーバックスから出版された
海堂尊さんの著書「死因不明社会」を読んだときでした。
人では死後に剖検が実施されるのはわずか2%代であり、多くの死因が明らかにされていない
ことに驚いたことを鮮明に記憶しています。
この本では死因不明社会によって引き起こされる色々な問題が提起されていますが、
人と同じことが動物にも多く当てはまると感じました。
一方、十数年前の当時の獣医療はまだまだ人の医療ほど発達しておらず、大学では剖検も
比較的日常的に行われていたので、あまり実感がわかない部分も少しはありました。
しかし、ヒトと動物を取り巻く状況は近年目まぐるしく変化しています。
このまま動物でも死因が明らかにされない状況が続くと、獣医師や動物の所有者(飼い主や
畜産農家など)にとって問題があるだけでなく、動物からヒトにもたらされる可能性のある
疾病を見逃してしまう恐れもあります。
日本では全国に17ヶ所の獣医大学があり、それぞれに病理学研究室があって様々な動物の
病理解剖が行われています。
しかし、いずれの大学も剖検数は年々減少しており、教育材料を確保するのに
四苦八苦していると聞きます。
大学でもそうであるならば、現場の動物病院や畜産農家ではなおさらのことだと
想像できます。特に動物病院では、
以前と比べて飼い主の意識が変化してヒトとの結びつきがより強くなり、
剖検の同意が飼い主から得られにくくなっているという状況です。
また、臨床獣医師側も飼い主の心情を察して剖検の話を切り出しにくいという
こともあります。
一度は剖検の依頼があったけど気持ちの踏ん切りがつかず、剖検できなかったという
事例も頻繁に遭遇します。
しかし、近年の獣医療の急速な進歩に伴って治療がますます複雑になっていることから、
治療効果の判定や獣医療のさらなる発展のためにも、剖検はもっと積極的に行われる
べきだと考えています。
動物病院や動物園・水族館の場合、多くは現場の臨床獣医師によって剖検がなされます。
せっかく大切なご遺体を剖検させていただくのですから、本来であればきちんとした
獣医病理学の専門家が剖検をするべきですが、大学を除けば獣医病理の専門家が勤務
する動物病院や動物園・水族館は非常にまれです。
残念なことに、現場の臨床獣医師が実施する剖検は、系統だった病理解剖ではなく、
単なる解体であり、記録が不十分なことが多々あります。
科学的に物事を捉え、考えていくためには、先ずはきちんとした記録、すなわち剖検所見を
取ることが重要です。
患者の治療を担当した臨床獣医師ではない第三者が、客観的な視点で患者の病態や死因を
評価するためにも、剖検をもっと獣医病理学の専門家に委ねてほしいと思っています。
私は日常的に動物病院、動物園や水族館、畜産農家、動物実験施設、もしくは野外に
出向いて剖検をしたり、あるいは持ち込まれた様々な動物を剖検していますが、
臨床獣医師や飼い主をはじめとする動物の所有者の想いは本当に様々です。
解体ではなくきちんと実施された剖検は、その後の獣医療の発展に間違いなく貢献するもの
ですし、病態解明を通して同じ病気で苦しむ多数の動物たちを助けることにもつながります。
飼い主にとっては、どのような経緯で亡くなったのかを理解することで、
死を納得することにもつながります。
前置きが非常に長くなりましたが、Aiは獣医学においても、剖検率低下を補うものとして
非常に重要な選択肢になるものと思います。
最近では獣医系の学会や研究会でも、Aiを取り入れた症例が出されることがほんの
少しずつですが散見されるようになってきました。
ただし現段階ではまだ試験的な取り組みといったところです。
Aiが獣医療においても有用な診断ツールとなるにはもう少し時間がかかるかも
しれませんが、将来的には日常で実施が可能となることが期待されます。
動物はヒトと違って全身を被毛で覆われているため、外から見ただけで体表や皮下
あるいは体内の状態を判断することが困難です。
また、体の不調を自ら訴えることができないため、予期しないところに病変が
隠されていることもよくあります。
現状では、頭部の剖検(特に脳)を拒まれることが多々ありますが、頭部以外の臓器を
くまなく調べても異常がなく、脳に病変があったのではないかと考えられる症例も
ときどきあります。
Aiでは、事前に頭部を死後画像検査によって確認することで、不要な頭部の剖検を
避けたり、あるいはAiがきっかけで頭部の異常を発見することにつながるかもしれません。
Aiは、今後新たな学問となるであろう獣医法医学(法獣医学)にも威力を発揮できます。
動物虐待や人への犯罪の予兆を探知することにつながります。
幸いなことに、現在では民間の動物病院でもCTを導入するところが増えてきました。
動物園や水族館でも、CT装置はありませんが近隣の動物病院にCT検査を依頼することが
日常的になりつつあります。
MRIも大学病院だけでなく、東京や大阪、名古屋などの大都市圏では導入している
施設も何件かあります。
Aiが実施される下地はすでに出来上がっています。
ここで注意しないといけないことは、Aiが必ずしも剖検の代わりになるということでは
ありません。
不幸にして亡くなった動物の死因や死に至った経緯を明らかにするためには、
様々な検査をする必要があります。
動物の死因を明らかにするためには、まずは剖検をして肉眼観察をするとともに、
必要な臓器を採取して、その後に病理組織検査、微生物検査、化学分析などいくつかの
検査を実施します。
最終的にそれらの検査結果を総合的に判断して病態や死因を考察する必要があります。
剖検(病理解剖)のみによって死因が判定できることは、実は非常に少ないです。
きちんとした剖検を行なって適切な臓器の採取がされていなければ、その後に実施される
様々な検査が無駄になってしまうことも少なくありません。
剖検は、その後に実施される様々な検査の要(かなめ)となる極めて重要な作業です。
しかし、動物の場合、人と違って生前の情報がかなり限られています。
事前に得られる情報が多ければ多いほど、適切な剖検が実施でき、
正確な病態把握につながります。
何も情報がない状態で剖検を行うことは、地図なしで目的地にたどり着くことに等しい。
これまでは剖検が主軸だった死後の検査に、Aiも取り入れることで得られる情報が増え、
亡くなった動物の死因や病態をより正確に把握できます。
死後にまずAiを実施することで、その後の道筋をつけることが期待されます。
Aiはまた、画像データとして保存しておくこともでき、後から検証することも可能です。
そのようにして得られた死後の情報は、獣医学や獣医療の発展に大きく貢献できる
ものであり、残された動物のためにもなります。
現段階では獣医学におけるAiの位置づけは定まっていませんが、まずはAiと実際の
肉眼所見を対比させることから始めて、今後Aiが獣医学においても発展していくことを
期待したいです。
動物の死因を明らかにすることは、人や動物、それを取り巻く社会、
そして自然環境のためにも極めて重要なことです。
「死」から「生」を学ぶ
テレビでは生きた動物に関する話題は豊富にありますが、動物の
死を扱ったものは少なすぎると感じています。
いま、「死」から「生」を学んで人や動物、自然環境がより良く
生きていくことを模索するときが来ているのではないでしょうか。